「働きながらの国試対策、いつから始めたら間に合うんだろう…」
「ただでさえ忙しいのに、勉強時間なんて確保できるわけがない…」
そんなふうに思っていませんか?
はじめに:仕事と勉強の両立、本当にできる…?
通信制や定時制の学校に通いながら、国家試験(国試)を目指すあなたは、たくさんの不安を抱えているのではないでしょうか。
仕事、学校の課題、そして人によっては家事や育児。 毎日が目まぐるしく過ぎていく中で、「国試対策」という大きな壁が迫ってくるプレッシャーは、本当に大きいですよね。
でも大丈夫です。
僕も同じ道を通り、働きながら国試に合格しました。
この記事では、僕が実践した**「いつから始めるべきか」という最適なスケジュール**と、時間がない人でも実践できる超具体的な勉強法を、体験談を交えてご紹介します。
結論:国試対策は「本番の1年前」から始めるのが最強の理由
色々な情報があって迷うかもしれませんが、僕の結論は**「国試本番のちょうど1年前から、少しずつ始める」**のが最適です。
「え、そんなに早くから!?」と思うかもしれませんが、これは1年間ずっと全力で走り続ける、という意味ではありません。 むしろ、「燃え尽き」を防ぎ、着実に合格レベルに到達するための、最も効率的なスケジュールなのです。
- 最初の半年: 助走期間。勉強を「習慣」にするのが目的。
- 残りの半年: 本格期間。苦手分野を潰し、得点力を上げていく。
この長期的な計画こそが、時間のない社会人学生が、余裕を持って合格を掴み取るための鍵となります。
【時期別】僕が実践した国試対策ロードマップ
では、具体的にどう過ごしていくのか、僕の体験を元にしたロードマップをご紹介します。
(1年生・準備期間):「学校の宿題=国試勉強」と心得る
特に通信制の1年生は、紙上事例などをまとめる課題(宿題)がたくさん出ます。 実は、この宿題こそが、最高の国試対策になっています。なぜなら、国試で問われる「状況設定問題」を解くための、思考力が徹底的に鍛えられるからです。
「ただの宿題」と思わず、「これが国試に出るんだ」という意識で、一つひとつ丁寧に取り組むことを強くおすすめします。
1年前〜半年前(基礎固め期間):まずは毎日5分、問題に触れる
いよいよ国試を意識した勉強のスタートです。しかし、ここでいきなり頑張りすぎる必要はありません。 大切なのは、**「毎日少しでも国試の問題に触れる」**という習慣をつけることです。
僕はこの時期、通勤電車の中で、スマホの国試対策アプリ(クエスチョン・バンクなど)を使って、必修問題を1日5問だけ解くことを日課にしていました。 たった5分でも、毎日続ければ絶大な力になります。

半年前〜直前(本格対策期間):自分の「苦手」を潰していく
夏が終わり、秋風が吹き始める頃(8月〜9月)、いよいよ本格的な対策に入ります。 模試などを受けて、自分の苦手分野を徹底的に分析しましょう。そして、その苦手分野を一つひとつ潰していく作業に集中します。
この時期に基礎が固まっていると、焦らずに自分の弱点と向き合うことができます。
【超具体的】時間がない僕が生み出した「どこでも勉強法」
僕が実際にやってみて、効果絶大だったスキマ時間の活用術を2つご紹介します。
1. 「トイレ」を最強の暗記部屋にする
一番プライベートな空間であるトイレは、最高の暗記部屋になります。 僕は、覚えにくい解剖図や、計算式、ゴロ合わせなどを書いた紙を、トイレの壁に貼っていました。
毎日必ず目にするので、意識しなくても勝手に頭に入ってきます。家族には少し驚かれますが、効果は保証します(笑)。
2. 「耳」もフル活用する。音声学習のススメ
通勤中や、家事をしながらでもできるのが「音声学習」です。 今はYouTubeなどで、国試対策の要点を解説してくれる聞き流し動画がたくさんあります。 参考書を開けない時間も、耳だけは勉強モードにしておく。この積み重ねが、大きな差を生みます。
おすすめの国試対策YouTube
https://www.youtube.com/@tabaemon (たばえもん様)
https://www.youtube.com/@nekocan_nekowo (ネコかん様)
まとめ:継続こそが、合格への一番の近道
働きながらの国試対策は、決して楽な道ではありません。
しかし、早くから計画的に始め、自分なりの工夫でスキマ時間を見つければ、合格することは十分に可能です。
大切なのは、一度にたくさんやることではなく、毎日少しでも続けること。
僕もこの方法で、夢だった正看護師になることができました。
次は、あなたの番です。

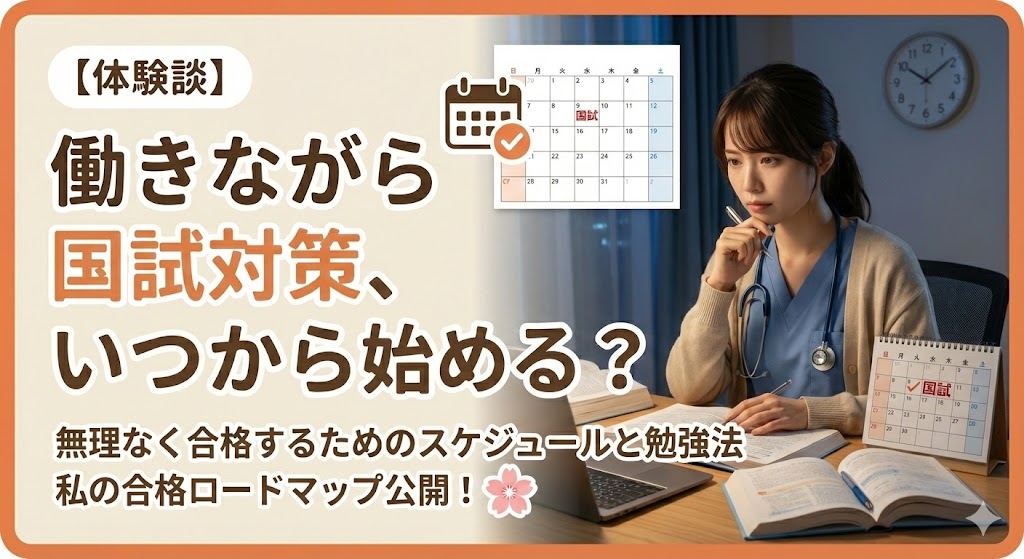
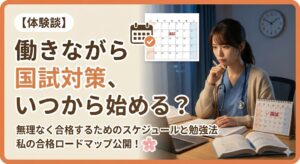
コメント